【夜葬】 病の章 -82-
――一九七〇年四月。
日本中、女性たちの悲鳴で染められていた。
ビートルズの解散である。
世の女性は、誰もが嘆き、悲しみ、涙に声を枯らした。
三月には日本のみならず、世界中を震撼させたよど号ハイジャック事件が勃発。
記念すべき七〇年代の開幕は、上半期の折り返しを待たず暗雲が立ち込めていた。
しかし、暗い出来事ばかりでもない。
大阪で日本万国博覧会が開催され、国内外から多くの人間が詰めかけ、連日大賑わいとなった。
各国のパビリオンはすし詰め状態。子供たちの間では万博に行ったかどうかがひとつのステータス化していた。
何度も足を運ぶ者も後をたたず、巨大なシンボル『太陽の塔』の足元には常に人がアリの大群のように犇めいていた。
まさに日本の経済はピークを迎え、戦争の記憶は国民から消え去った。
和服で過ごす者の数を洋服を着こなす者が大きく上回り、人々は歩きながら齧りつけるハンバーガーやコーラに舌鼓を打った。
老人たちは縁の下で碁を指し、ぼやく。「この国は変わってしまった」と。
菊池健一は、そんな戦後に生まれた。
今年で二四になる健一が『栃木ツツジテレビ』に入社できたのは、重役の父親のコネだ。
健一は、別にやりたいこともなく大学をでてプラプラしていたところを半ば強引に押し込められた。
しかし、やはり血か。
いざ勤めてみると、この仕事が肌に合っていると健一はすぐに感じた。
親の七光りだと散々周囲から陰口を叩かれたが、めきめきと才能は頭角を現し、同期の中でも健一だけが頭一つ飛びぬけていたのだ。
役職こそアシスタントディレクターの肩書きだが、実際の権限はディレクターに近い。
父親の威光と健一自身の才覚が、暴力的に融合し、局内でも健一の名は広く知れ渡っていた。
「それ、やりましょうよ」
制作会議の中で出た些細な案に健一が食いついた。
ロの字に囲む長机の端々から、局員たちの視線が集まる。どの瞳も、驚いたような、呆れたような、胡乱な印象のものばかりだった。
「菊池、お前正気か?」
健一より四年先輩にあたる宮園が口ひげをさすりながら、困ったように笑った。
「ええ、正気も正気。本気ですよ」
局員たちから溜め息とも嘆息ともつかない声が漏れた。
無理もない。健一が興味を示したのは、『失踪したクルー』の話。それも一五年も前の話だ。
一九五五年は、栃木ツツジテレビが開局してまだ間もないころだった。
テレビはどの局も合戦の様相で、より過激で、より面白いものを模索していた。
報道規制のようなものもほとんど存在しなかった時代で、この年、葛城というディレクターが四人のクルーを引き連れ、とある山の集落へと取材に行った。
「企画も通して、葛城さんたちは山へ行きました。その時の上長が当時、プロデューサーだった僕の父です。正直、その時のことは知りませんし、この案件自体初めて聞きましたが、情報の出どころならありますよ。父に聞きます。それで消えた葛城さんたちを追う特番を作りましょうよ」
誰もが「またか」という顔を浮かべ、ある者はそれを悟られまいとうつむいた。
無意識なのか無自覚なのか、健一は話の端々に父親の名を出す。
それが彼らを黙らせるのだ。
「わかったわかった。だが企画を通すには、ちゃんと企画書に起こしてこい。菊池取締役に話を聞けるというなら、そう難しくもないだろう。お前のことだから心配はしてないが、ちゃんと面白いのをあげてこいよ」
髭のプロデューサーの言葉が結びとなり、会議は終わった。
葛城らの失踪事件は、栃木ツツジテレビ局内でも有名な話だ。テレビは様々な危険と隣り合わせで、事件まがいの出来事は日常茶飯事だった。
だがその中にあって、五人の人間が失踪したのは異例だ。それも、その後の情報が一切ないという。
彼らがどこで、どうやっていなくなったのか。その片鱗すらわからない。
ただひとつ、わかっていることは視聴者からの投書が元で件の山の集落へと向かったのだという。
健一だけではなく、局員のほとんどがこの程度のことしか知らない。
だが、怪談のようにエピソードだけが独り歩きし、一五年前の出来事がいまだに語られるのだ。
それでも、この事件は前述の通り怪談扱いしかされていない。誰もまともにこれを取り扱おうなどと言い出す人間はいなかった。健一を除いて。
「葛城のことには一切かかわるな」
それは、健一にとって寝耳に水の一言だった。
父、菊池八郎は失踪事件について話を聞きだそうとする健一にぴしゃりと言い離したのだ。
「ちょっと待ってよ、父さん。かかわるな、ってなんなんだ」
「なんでもいい。あの件にはかかわるんじゃない。わかったな」
八郎は多くを語ろうとせず、健一に取り付く島も与えなかった。
そのはっきりとした意思に、健一は余計にムキになる。
「それだけじゃわからないだろ! 僕の企画が番組になるんだよ! 頼むよ、教えてよ父さん!」
健一は食い下がった。
だが八郎は「だめだ」の一点張り。頑なだった。
噴き出す不満を表情一杯に表し、口にも出しながら、健一はいつもと違う父の態度に違和感を覚えていた。
ベビーブームの時代にあって、菊池家の子供は健一だけだ。
そのせいか健一は、この歳になってもずいぶんと甘やかされて育ってきた。
欲しいものはなんでも買ってもらえたし、行きたいところにはどこにでも行けた。
大概のわがままも通ったし、親に叱られた記憶もほとんどない。
それなのに、父は初めて健一に硬い意思を示し、事件のことについて一切口を開かなかったのだ。
「諦めろ、健一。私は話さん」
「僕がどうなってもいいんだな、出世のチャンスかもしれないのに!」
「それは惜しいがまだ早い。もっと下積みを詰め」
「もういい!」
捨て台詞を残し、健一は部屋へ駆け込んだ。
――なにかある。父さんは、それを知っているんだ……。くそっ、絶対に掴んでやるからな!
スポンサードリンク
関連記事
-

-
【蔵出し短編】アキレス健太郎 4
アキレス健太郎 3はこちら 「あの、三浦さん!」 本館の外に
-

-
ホラー小説 / 食べる その2
■食べる その2 (その1はこちら) 「今日はみなさん、陽太のために来てく
-
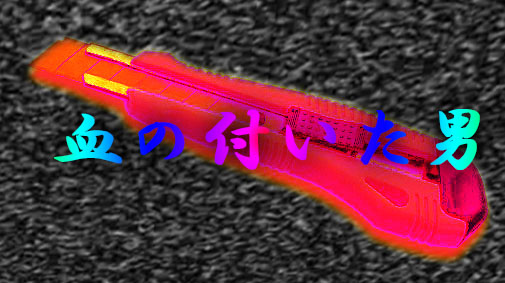
-
ホラー小説 / 血の付いた男 ①
■いつもの帰り道 ホームを降りると
-

-
【夜葬】 病の章 -21-
-20-はこちら その日の晩、美郷がいなくなっ
-

-
ホラー小説 / お見舞い その1
■悪夢は突然に 「卓也! 卓也! お父さんだぞ! ほら、しっかりしろ!」
-

-
【夜葬】 病の章 -87- 最終話
-86-はこちら 栃木に帰った健一は、翌日も会社を休んだ。
-

-
【連載】めろん。67
めろん。66はこちら ・綾田広志 38歳 刑事㉔ タンスの抽斗を上か
スポンサードリンク
- PREV
- 【夜葬】 病の章 -81-
- NEXT
- 【夜葬】 病の章 -83-










