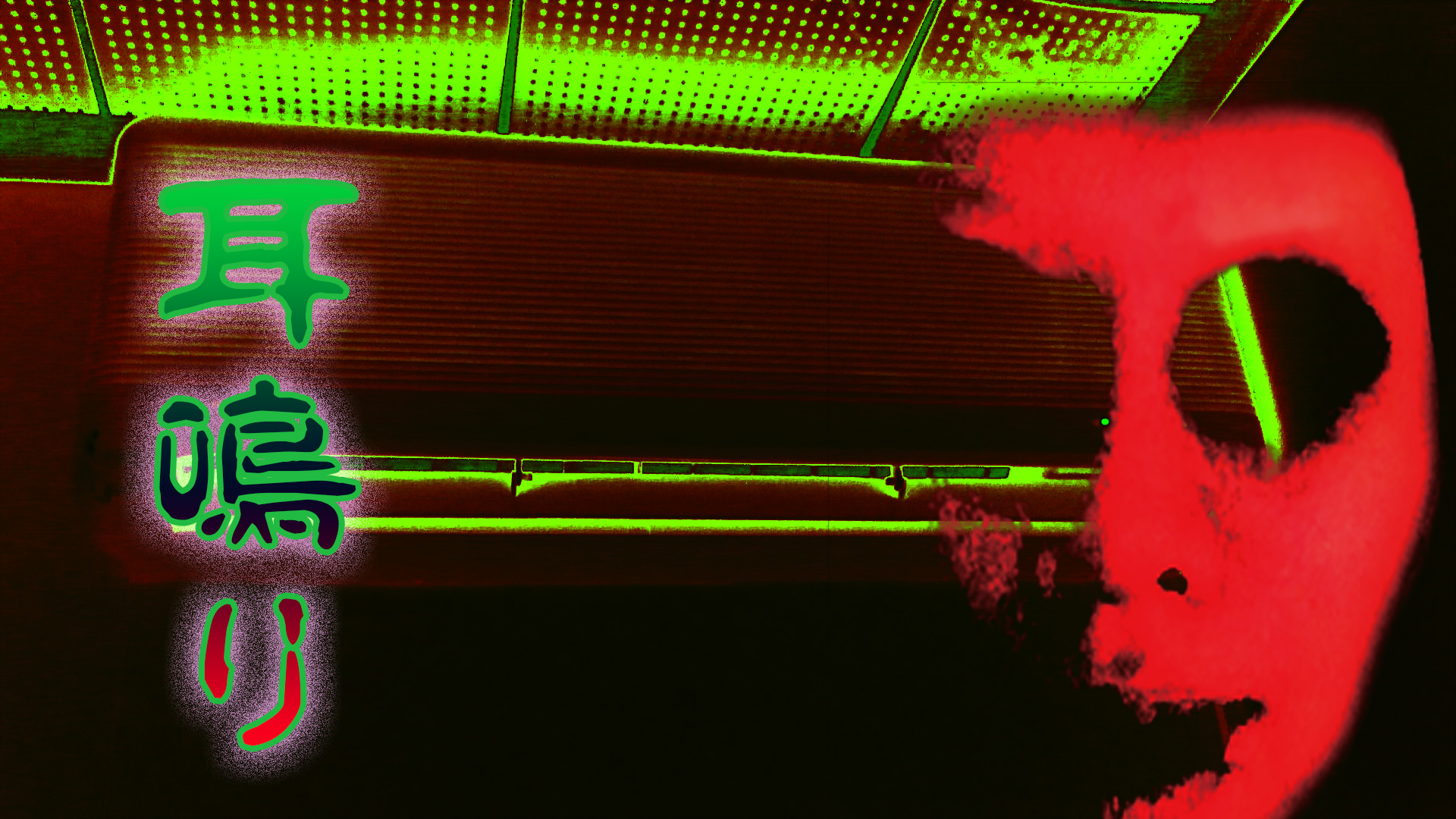【夜葬】 病の章 -83-
社内で健一の企画が立ち消えが噂されはじめた七月初旬。
半袖の町で、ジャケット姿の健一の姿はひときわ目立った。
ふと見上げた鉄塔。赤くもなく、思ったよりも高い。東京タワーではなく、それは通天閣。健一は大阪にいた。
夏の大阪の町は、栃木よりも暑く感じた。
だが反面、活気はこちらのほうが良いように思う。
だらだらと滝のような汗が、健一の襟を濡らし、商人の客引きの声があちこちで飛び交う。そこに、黒川元はやってきた。
「ええっと、菊池さんですかぃ?」
大阪の町には不釣り合いな、栃木訛りの残る口ぶりで元は健一に話しかけた。
健一は一礼すると、お暑いですね、と親しげに返す。名刺は渡さない。
「この度はご足労、すみません」
「いやぁ、同郷の人間に会うことなんてそうそうないもんでねぇ。嬉しいですよ。……いや、嬉しいなんていうと不謹慎ですな」
健一は微笑みながら首を横に振る。あくまで真摯にふるまうことに注力した。
「どこか、涼しいところに移動しましょうか」
来る途中に喫茶店があったはずだ、と健一は元と共に歩いた。
店に向かう途中、話すのは暑さと天気、それに万博の話ばかりだった。
健一自身、大阪にやってくるのは初めてではない。それゆえ、万博効果で賑わう人の多さはありありと感じていた。
「これがずっと続けば、景気もいいんでしょうけどね」
「冗談じゃないでさぁ。ゴミゴミしているだけでちっとも」
そう言った延長で、元は大阪に移りずんだ経緯を語った。
要は人の多さに辟易したのだそうだ。そういう意味では大阪もそう変わらないのでは、と訊くと「便利だから都会がよかった」と言う。
そういう意味では、まだ東京より人が少ない。なのにこの万博ブームで変わらないくらいの人が犇めいている現状に憂いているようだ。
「いらっしゃいませ」
喫茶店はクーラーが効いていて、外の地獄とは相反する天国を擁していた。
急激に冷えてゆく汗が心地よく、ワイシャツのボタンを外し、ネクタイを緩めたい欲求に駆られたが健一はなんとか耐えた。
「そんな暑苦しい恰好せんでも。背広くらい脱いだらどうです」
「いえ、大丈夫です」
本音が喉元まで出そうになるのを堪え、健一は店員にアイスコーヒーを注文した。
「アイスコーヒーなんて栃木でも飲めるでしょうに。せっかく大阪に来たんだぁ」
元はそう言って、健一の注文したアイスコーヒーを勝手に取り消すと、ミックスジュースをふたつ頼んだ。
「ミックスジュース?」
「そっちじゃあんまり聞かないだろうねえ。こっちじゃ喫茶店といったらこれなんですわ」
にこり、と笑う笑顔は屈託なく少年のようだった。
健一はその人懐っこそうな笑顔に、緊張が氷解していくのを感じた。
『黒川元は、鈍振村の出身である』
その情報を入手したのは、テレビ業界とは全く関係のない男からだった。
男は、健一の父・八郎と旧知の仲で年に数度、菊池家に訪れるほど健一とも顔見知りだった。
葛城失踪と鈍振村について、一切の口を閉ざす八郎からの情報は期待できないと悟った健一は、こっそりとこの父の友人に連絡を取った。
そうすると健一の思惑通り、父の口から入手できなかった情報が手に入ったのだ。
それが『黒川元』という男の名。
酒の席、酔った勢いでつい口走ったらしい父は、この男についてこう語ったという。
『黒川元という男から投書が来たのがきっかけで葛城たちは鈍振村と夜葬という風習について知った。そして、のちのロケに繋がってゆくわけだが……あんなことになるなんて』
たったこれだけの情報。
だが名前と投書があったという手がかりだけあれば、今の健一にはそれ以上の情報を掴むのはそれほど困難ではない。
他局ならまだしも、自局での事件。当時の関係者だって現役の人間は相応にいる。健一の父だってそうだ。
そう思った健一は、すぐさま父と同期、その前後のテレビマンを調べた。
そして、ひとりひとり聞きまわったのだ。
だが誰の口も堅かった。とんとん拍子で真相に近づけると思った健一の計画に暗雲が立ち込める。
企画会議から3ヵ月が経とうとしていたとある時、ようやく口を開いた人間に出会う。
それは女性だった。
結婚を機に退職し、その後専業主婦となるが後に離婚。
女手ひとつで生活を切り盛りする彼女が、口を開くのはある意味自然なことだった。
そうして、健一は掴んだのだ。
『黒川元は鈍振村の出身者で、(一九五五年当時)現在は村を離れ宇都宮で暮らしている』と。
そこからは手間はかかるが難しい作業ではなかった。
黒川元が栃木ツツジテレビともうひとつ、投書を送ったとされる新聞社の人間。そして、元が勤めていた職場。
それらから今は元が大阪で勤めていると掴んだのだ。
「弁護士さんっちゅうのは大変な商売ですなぁ」
「え? ああ……いえ。とんでもない」
健一は、元と初めて電話でコンタクトを取る際、自分の身分を『弁護士』であると偽っていた。
彼なりのテレビマンとしての勘が、『マスコミ業界の人間だと知られるな』と言っていたのだ。
それならば、どんな立場ならすんなりと口を開くのか。健一は考えた。
試行錯誤の結果、『失踪した葛城の遺族の代理』としての弁護士を騙ることを思いついた。
かなり強引な手段だと思ったが、この件について動いているのが健一ひとりだということも加味し、要所要所で強引にいくしかなかった。
「それでですね……葛城さんのご遺族からの意向で、どうしてもなにがあったのかを知りたいということでして。ただ、鈍振村という場所の情報があまりにもなさすぎてですね、場所も特定しかねていまして。それで勝手ですが投書の名にあった黒川さんにお話をお聞かせ願おうと」
「そうですかぁ。それはそれは……わたしなんぞの話でよければ」
――【ご遺族】という言葉に反応しなかったな。やはり葛城さんたちが死んだ、と思っているのか。
これが邪推ならそれはそれで構わない。しかし、無視できることでもないと健一は思った。
運ばれてきたミックスジュースは、健一の初めて見る不思議なものだった。
ドロリとした卵色のジュースに氷が浮いている。ビールのように泡を冠にしたその姿からは、まったく味が想像できない。
「まあ、飲んでください。長い話ですんで」
元の口ぶりから、健一は話を聞きだせそうだと思わず破顔しそうになる。
それを堪えるため、得体の知れないミックスジュースに喉に流し込んだ。
妙なのどごしだったが、見た目よりマイルドで美味だった。
スポンサードリンク
関連記事
-

-
【連載】めろん。25
めろん。24はこちら ・大城大悟 38歳 刑事① 綾田の話を聞いてい
-

-
ホラー小説 / 食べる その2
■食べる その2 (その1はこちら) 「今日はみなさん、陽太のために来てく
-

-
【夜葬】 病の章 -55-
-54-はこちら いいじゃ
-

-
【連載】めろん。18
めろん。17はこちら ・破天荒 32歳 フリーライター ヴォイニ
-

-
【連載】めろん。15
めろん。14はこちら ・綾田広志 38歳 刑事⑤ 玉井善治は寝室のベッドでひ
-

-
【連載】めろん。56
めろん。55はこちら ・破天荒 32歳 フリーライター⑪ 広
-

-
teller Xmas
■12月18日 いよいよこの時がくる。 彼女と付き合って初めてのXmas。
-

-
【夜葬】 病の章 -57-
-56-はこちら ふぅん。
-

-
ホラー小説 / サトシくん
■バイト先の女の子 僕は数週間前か
スポンサードリンク
- PREV
- 【夜葬】 病の章 -82-
- NEXT
- 【夜葬】 病の章 -84-