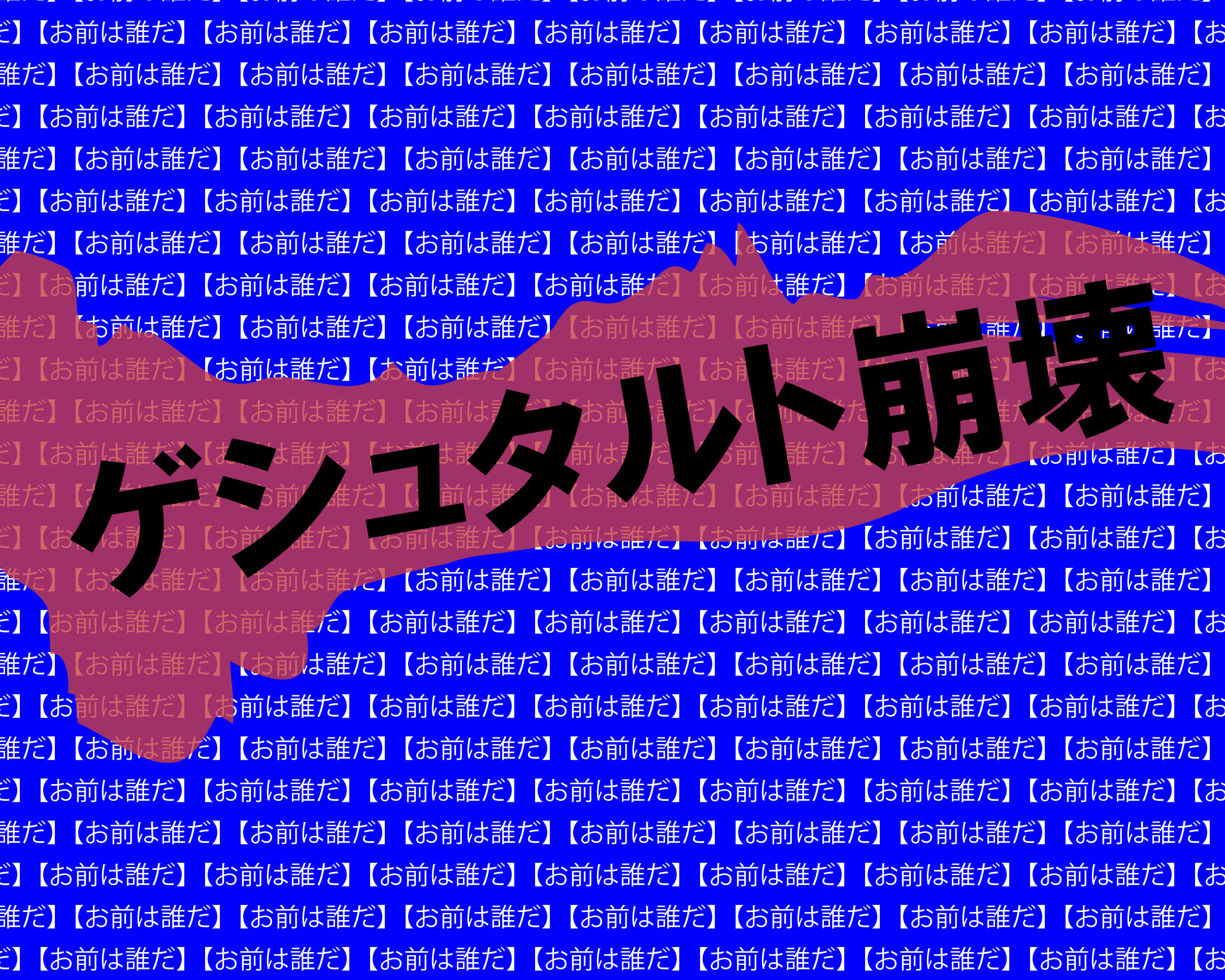【蔵出し短編】アキレス健太郎 1
アキレス健太郎 1(全4回)
13日の金曜日といえばなにを連想するだろう。
ホッケーマスクの殺人鬼は当然として、あとはなにがある?
キリストの命日とかいわれているけど、本当のところは磔にされた日らしい。だから忌み日の数字として『13』が嫌われている。とにかく不吉だということだけは確かだ。
信仰の自由を認めている我が国で、キリスト教信者以外の人間がこれを忌み嫌っているというのはどうにも失笑ものだが、それとは違う意味で13日の金曜日が嫌われている場所がある。
それがここ、真宵坂スポーツセンターだ。
スタジアム型の陸上競技場に大型の体育館、プールにテニスコートもあれば道場、多目的ルームもある。各所空調設備は万全だし、プールも季節を問わず温水で水質も上々だ。
サークル活動も盛んで、大人子供を問わず、年中アスリートや予備軍が賑わっている。大きな大会なども開催されるような、地域を代表するスポーツ施設だった。
それなのに、だ。
「今月は13日の金曜日があるな。わかっていると思うがその日は全職員、出勤厳禁だぞ。当施設も一日閉鎖する」
主任の言葉に職員たちが体育会系よろしくのハツラツとした返事で返す。見回しても誰ひとりとして疑問を口にするものも、顔にだすものもいない。
それをごく自然なこととして受け入れている証拠だった。
「当番はどうしようか。誰か志願するものはいないか」
再び見回す、手を挙げるものはいない。
13日の金曜日は全館休業日に設定されているが、だからといって無人にするわけにはいかない。この日だけはふたりだけ当番を決め、持ち回りで宿直をする。施設の大きさに対して警備に割く人員が少なすぎる。これもまたここではごく普通のことなのだ。
宿直といってもやることは多くない。主な仕事は点検と保守、施設の見回りだ。それも日に数度だけで深夜はイレギュラーが発生しない限りは寝ていていい。ただ施設の部屋に泊まっていればいいだけの楽な仕事だ。
それも特別手当つき。ぼくから言わせれば手を挙げないほうがおかしい。
「案の定誰も手を挙げないか」
状況を読んでいたのか、諦観めいた表情で主任は溜め息をついた。
好条件なのにもかかわらず、ぼくが手を挙げなかったのは不自然なほど誰も挙手しないからだ。特別手当のことも、楽な仕事のことも周知のはずだった。
それなのに誰もはなっから挙げるつもりがない。その状況に及び腰になってしまったというわけだ。自分だけが手を挙げるのはどうも気が引ける。
「もっと好条件に吊り上げなければならないかな」
つぶやく主任に職員のひとりが「意味ないですよ」と反論した。
そこから言い合いになるかと思いきや、主任はあっさりとそれを呑み込むと黙り込んでしまった。気味の悪さに拍車がかる。
「まあまだ二週間近くある。気が変わったら私まで言いにきてくれ。誰もいない場合は悪いがくじ引きになる」
場の空気がわずかにどんよりと重くなった気がした。ふと主任と目が合う。
頼むよ、と言っている気がした。むしろ頼んでくれたほうがぼくとしては気が楽なのだが。
「帰りメシでもいかね?」
職場の先輩職員佐竹が肩を叩く。
「あれ、佐竹さん今日は奥さんいないんですか」
「そうなんだよ、子供がおたふくやっちゃってさ。ふたりで実家に帰ってら」
「それは大変ですね。いいですよ、いきましょう」
ぼくが真宵坂スポーツセンターに配属されて、半年が過ぎようしていた。
新卒はすべからくして会社が運営する各施設に配属され、まる一年適正を磨く。そしてその後正式な配属が決まる仕組みになっていた。いわば今は試用期間のようなものだ。
さらにあとから聞くところによると、スポーツ経験がある新入社員は優先的にここへ配属になることが多いらしかった。
事実、僕も学生時代は陸上に捧げてきた身だ。今でも走ることはやめられず、社会人チームにも所属している。そういうわけでここに配属になったのは願ってもないことだった。13日の金曜日の件を除いては。
「最近はようやく慣れてきましたけど」
ハイボールのジョッキグラスを傾け、愚痴にも似た声を漏らす。苦笑いを浮かべながら佐竹が焼酎を割りばしでかきまぜた。
「暑っ苦しい名前しときながら湿った顔すんなよ」
「暑っ苦しいとかいうの佐竹さんだけですよ」
食事に訪れた居酒屋は雑然としている。空席も目立つが店内の活気がそれを補っている。
「ほら佐竹さんだっていつもその態度だし。誰も詳しいことはなにもいわないから、ぼくも諦めましたよ。13日の金曜日のこと」
ここまで煽っても佐竹は動じない。他の話題なら大人気ないほど一喜一憂してみせるというのに、やはり不気味だ。
――真宵坂スポーツセンターにおける13日の金曜日とは。
全館休業という措置以外に理解に苦しむのは職員たちの態度だった。
主任をはじめとした職員たちはとにかく13日の金曜日がなぜ休館なのか、どうして営業してはいけないのか、その理由を決して口にしない。
口にしない上に当番は避けるのだ。意味がわからないし納得もできない。
付け加えておくが、職場でぼくが浮いているわけでも避けられているわけでもない。職場いじめだなんてもってのほかだ。
この件を除けばむしろ普通より上手くやっている。同僚間の交流もいい。
「それなのに頑なに口を噤むのはなんでなんですか。13日の金曜日がとにかく真宵坂スポーツセンターにとってダメな日っていうのはわかりました。だけどその理由がわからないんじゃどうしようもない。大体、利用者に聞かれたらなんて答えればいいんですか」
自分で言っておきながら、正直それはないな、と思った。
ここに勤めてから一度だって、『なぜ13日の金曜日が休みなのか』という質問を受けたことがない。つまり利用者の間でも周知の事実なのだ。
利用者も職員も知っていて、ぼくだけが知らない。これで不満が噴出しないわけがない。ただ我慢してきただけだ。
「……今日、主任が当番の話してたじゃないですか。あの時、誰も手を挙げない中、主任と目が合ったんです。正直、条件だけ見たらやってもいいな、って思ってます」
バカ、やめろって! 佐竹が声を上ずらせた。
「それでも手を挙げなかったのはそんな好条件なのに誰も手を挙げなかったからです。あの場で自分だけ手を挙げる勇気はないですよ。でも、主任が助けを求めるような目でぼくを見て、目が合った。もしも主任がぼくに話を持ちかけてくるようであれば受けるつもりです」
一息で吐きだすとハイボールを飲み干した。意志表明の代わりにジョッキの底を叩く。
なにか言おうと半開きになった口のまま、佐竹は観念したように前のめった体勢を整える。
「話せることは少ないぞ」
「えっ、話してくれるんですか」
「お前の不満はもっともだよ。俺も最初はそうだった」
佐竹は店員を呼び止めると空になったジョッキを指差し、おかわりを注文した。
礼を告げると佐竹は溜め息まじりに訥々と語った。
「宿直当番な、お前の言う通り好条件だから普通なら希望者が殺到しておかしくない。主任のあの困り果てた顔色を見るとこれからさらに条件は吊り上がると思う。でも無駄だな」
そういえば主任に「意味ないですよ」と誰かが投げかけたのを思いだした。今思えば、佐竹に声が似ていた。
「まず、このことを他人に話すのは危険だ。つまりこれ以上聞くなら俺もお前も危ない。それでも聞くか」
「危ないって……それだけ聞いたってわけがわからないですよ。内容を聞いてこそそれが判断できるじゃないですか。話を聞いただけでなにか起こるってわけじゃないですよね」
「そうだと言ってる」
まさか、と笑う。佐竹が笑っていないのを見てすぐに笑みを噛み殺した。
「どういうことなんですか。話すだけで危ないって、何系の話ですか」
「なに系って……そうだな、聞くと危ない系だ。でもお前は聞かないともっと危なそうだな」
話が要領を得ない。主語を隠したまま判断しろというのは無茶だ。
だが話を聞くだけで危険だというのは納得ができなかった。その一点においてはいくら佐竹といえど信用できない。
「聞きます。覚悟はできてますよ」
だからこんな嘘が易々と言えたのだ。
ぼくの返事を受け、佐竹は深呼吸をした。そして、テーブル越しに顔を近づけるとひそひそと小さな声で話し始める。
どこか滑稽に思えて、笑いそうになったが寸でで食い止めた。
「アレに自分の話をしていると気づかれるとまずい。ここは居酒屋の客でにぎやかだから多分大丈夫だと思うが」
「アレって?」
「アレはアレだ。いいか、13日の金曜日に休業にしている本当の理由はスタジアムに誰も近づけないためだ。全館閉めているのは万が一のことを考えてのことなんだ」
「スタジアムに近づけないためですか? スタジアムで一体なにが……」
キョロキョロと周りを気にしながら佐竹はさらに声を潜める。こんなに神経質にしている佐竹は初めて見た。
「これを見ろ」
気づけば手にスマホを持っている。言われるまま画面を覗き込むと短いテキストが表示されていた。
〈アキレス健太郎だ〉
ぼくは一瞬、固まってしまった。意味を理解するのに時間がかかった。スマホとにらめっこの結果、佐竹のユーモアだと気づいた。
「ちょっと佐竹さん、ふざけないでくださいよ。アキレス健太郎って……ぷっはは」
思わず笑いが込み上げる。誰も知らないようなマニアックな芸人の芸名かと思った。
ははは、と腹を抱えていると突然、烈しく視界が揺れた。
「お前、ふざけんなよ。笑いごとじゃねえんだよ」
「……へっ?」
佐竹に胸倉を掴まれ、鼻がくっつくほど顔を近づけられていた。
「さ、佐竹さん?」
「気付かれたらヤバイって言っただろうが。お前のために教えてやってんのになにへらへら笑って名前を口にだしてやがる!」
「す、すみません! でも名前を口にだしたからって気づかれたりしないですよ!」
佐竹の剣幕に【アキレス健太郎】という間抜けなネーミングのおかしさが吹き飛んだ。ふざけているのか真剣なのか、ぼくの胸中も混乱している。一体、どういう姿勢でこれを聞かねばならないのだろうか。
「お待たせしました。ハイボールです」
店員が注文したハイボールを運んできた。テーブルにジョッキを置く際、カタカタと鳴る不自然な音に思わず目を落とす。
大学生だろうか。アルバイトらしき女性店員のジョッキを持つ手が震えている。カタカタという音はジョッキの底が手の震えでぶつかる音だった。
自らの震えを止めようと店員は片方の手で震える手を掴み、空のジョッキを引き上げもせずに立ち去ってしまった。
その様子を前に、胸倉を掴んだ佐竹の手が緩む。
「ああ……最悪だ」
「佐竹さん?」
「これは気づかれたわ。お前なんか気にかけんじゃなかった」
佐竹は持ちあげた尻を椅子に下ろすと脱力したように肩を落とした。
「わかりません……佐竹さん。せっかく話してくれましたけど、結局、なにがなんだか」
「いいよ。もう好きにしろ」
佐竹はテーブルに一万円札を置いて立ち上がった。
「え、佐竹さん!」
「帰る」
そう言って本当にでていってしまった。
ふたり分の料理と酒が置かれたままのテーブルにひとり残されたぼくは呆然と佐竹が座っていた椅子を見つめた。
すると奥の方から女の泣き声が聞こえてきた。
顔を上げて所在を探してみるとカウンターの奥から聞こえてくるようだ。さっきのアルバイトだろうか。
ふと妙な視線を感じ、振り返る。誰とも目が合わなかったが、ぼくは気づいてしまった。店の客らにチラチラ見られていることに。
――これは気づかれたわ。
佐竹の言葉が頭をよぎり、いたたまれなくなったぼくは運ばれてきたハイボールにひとくちもつけずに店をでた。
逃げだした僕の耳には、いつまでも女の泣き声がこびりついていた。
スポンサードリンク
関連記事
-

-
ハーメルンの笛吹きオンナ3 / ホラー小説
その1はこちら その2はこちら ■友人の前に
-

-
【9/20発売】『怨霊診断』序盤お試し公開
■いよいよ発売『怨霊診断』 どうも最東です。
-

-
【夜葬】 病の章 -58-
-57-はこちら 「ぼぅっとするな! 貸せ!」
-

-
【夜葬】 病の章 -27-
-26-はこちら 祭囃子が
-

-
【夜葬】 病の章 -82-
-81-はこちら ――一九七〇年四月。
-

-
teller Xmas
■12月18日 いよいよこの時がくる。 彼女と付き合って初めてのXmas。
-

-
忘れもの、ありませんか。
早朝の通勤ラッシュから逃れるようにして、駅のトイレに
スポンサードリンク
- PREV
- 【連載】めろん。49
- NEXT
- 【蔵出し短編】アキレス健太郎 2